どうも、ぽんせいです!
Blenderを始めて使おうとする時、最初にぶつかる疑問が「どこからダウンロードすればいいの?」というものです。調べてみると、Blenderには主に以下の2つのルートで入手する方法があります
- Blender公式サイト→Download — blender.org
- Steam版(Steamのプラットフォームから提供)
これら2つは、見た目や基本機能こそ同じですが、実際には導入方法やアップデートの仕組み、バージョン管理、アドオンの互換性など多くの点で違いがあります。この記事では、初心者でも迷わないように、両者の違いをわかりやすく紹介していきます。
Blender公式サイト版の特徴

長所
① アップデートのタイミングが早い(安定版リリース直後に即対応)
- 公式サイトでは新バージョンが出たら即ダウンロード可能。
- Steamは数時間〜数日遅れることがある。
- 最新機能やバグ修正をいち早く使いたい人に向いている。
② フォルダ構成がシンプルで自由
- 自分の好きな場所にインストールや解凍が可能(ZIP形式も利用可能)。
- 複数バージョンを簡単に並行運用できる。
- Steam版では通常、Steamのアプリディレクトリ内に強制される。
③ Steamなしで起動可能(オフラインでも完全に動く)
- Steam版はSteamクライアントが常にバックグラウンドで動く。
- 公式サイト版は、ネット環境やSteamログインに一切依存しない。
④ 純粋な「Blender」のみ(Steam独自の上書きや制限なし)
- 起動時にSteamのポップアップや通知が出ない。
- Steam特有の制限や干渉を避けられる(例:一部のショートカット制限など)。
⑤ スクリプトやアドオンとの互換性が安定
- 一部のBlenderアドオン(特に開発中のツールや外部ツール)はSteam版だとフォルダ構成の違いでエラーが出ることがある。
- 公式サイト版ならBlender公式の想定通りの環境で動作。
⑥ 学習資料やチュートリアルと同じ環境を作りやすい
フォルダ構成や設定もチュートリアルと一致するため、初心者にも親切。
多くの学習者やプロが公式サイト版を基準にしている。
短所
1. アップデートは手動
新しいバージョンが出た際は、自分でダウンロードし直す必要があります。更新通知も無いため、定期的に公式サイトをチェックする習慣が必要です。
2. 複数インストールの管理は自己責任
自由度が高い反面、複数のバージョンをインストールして管理するには多少の知識が必要です。初心者にとってはやや敷居が高いかもしれません。
Steam版Blenderの特徴

長所
1. 自動アップデート
Steamはゲームと同様にBlenderもライブラリ管理されるため、アップデートがあると自動で最新バージョンが適用されます。わざわざ新しいインストーラーを探しにいく手間が省けます。
2. 導入が簡単
Steamアカウントがあれば、「ライブラリに追加→インストール」の2ステップで導入完了。初心者でも安心です。
3. プレイ時間・使用履歴の記録
Steamの機能により、Blenderの起動時間や使用時間が記録されます。自分の作業時間を把握できるのは、継続的な学習やポートフォリオ作成に役立ちます。
4. コミュニティとの連携
Steam上で他のBlenderユーザーのレビューやガイド、フォーラム投稿を見ることができ、初心者にとっては学習のヒントとなる情報源が豊富です。
短所
1. バージョンの柔軟性が低い
基本的にSteamでは安定版のみが配信されるため、ベータ版や古いバージョンを使いたい場合は難しいです。
2. 複数バージョン併用が難しい
1つのアプリとして管理されるため、複数のBlenderバージョンを切り替えて使うことができません。開発用と商用でバージョンを分けたい人には不便です。
3. Add-onの互換性に注意
一部のユーザーからは、特定のAdd-onがSteam版で正しく動作しないという報告もあります。特にスクリプト系Add-onでは、Steamの環境設定が影響することもあります。
こんな人には公式サイト版がオススメ
- 開発中の最新機能を試してみたい
- 複数バージョンを同時に運用したい
- 外部ツールとの高い互換性を重視する
- アドオンやスクリプトを自由に使いたい
こんな人にはSteam版がオススメ
- とにかく簡単に導入したい
- 面倒なアップデート作業は避けたい
- Steamの実績や使用記録を活用したい
- Blenderを趣味で気軽に始めたい
公式サイト版とSteam版の使い分けアイディア
実は、公式版とSteam版を併用しているユーザーも少なくありません。以下は、実際に考えられる使い分けの例です
1. 普段の作業は公式サイト、最新版の確認でsteam版
これが、一番多いのかなと思います。Blender はアップデートすると、UIや機能の変更や追加をする場合があります。steam版をメインで作業すると、急にアップデートされて作業が再開しにくくなります。なので、自動でアップデートされない公式サイトでメインの作業をして、アップデートが配信されたら、steam版で確認して違いを見るのがオススメです。
2. ポータブル版をUSBなどに保存して持ち運び
公式サイトから取得できるポータブル版(ZIPファイル)は、USBメモリなどに保存して持ち運ぶことができます。外出先や別のPCでも自分の環境で作業できるのは便利です。
3. 講座・教育用にSteam版を使用
教育機関や講座でBlenderを教える際には、Steam版を使うとインストールが簡単で、生徒がすぐに学習環境を整えられるというメリットがあります。
4. Blenderを複数アカウントで使い分ける
Steamではアカウントごとに使用時間などのデータが記録されるため、家族やチームでBlenderを共有する場合に便利です。一方で、公式版は完全にユーザーごとのフォルダで管理できます。
まとめ:どっちを使うべき?
初心者にとって、簡単に始められるのは「Steam版」です。自動アップデートは効率的で、インストールも簡単なので、すぐに3DCGを始めたい人に最適です。
一方で、仕事で使いたい、複数バージョンを使い切りたい、ベータ版を試したいといった用途では、公式版が最適です。
どちらも無料で使えるので、最初はSteam版で始め、慣れてきたら公式サイト版に移行するというステップもアリです。それぞれの優れた点を理解して、自分に合った方を選んでみてください!



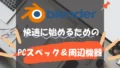
コメント