どうも、ぽんせいです!
Blenderを触っていると、プリミティブの中にひときわ異彩を放つ「モンキー」という項目を見たことはありませんか?立方体やUV球と並んで突然現れる猿の顔。その正体こそ「スザンヌ」です。
この記事では、Blenderのアイコン的存在とも言えるこのスザンヌについて、その由来、歴史、ちょっとした豆知識、そして実際の活用方法まで、深堀りしてご紹介していきます。
スザンヌとは何か?
スザンヌは、Blenderに標準で搭載されている3Dモデルで、いわばBlender版のテスト用モデル。他の3DCGソフトで有名な”Utah Teapot(ユタティーポット)”に相当する存在です。
操作メニューから「Shift + A」で追加できるオブジェクトのひとつで、形状はお猿さんの頭部。実際に追加してみると、そのデフォルメされた顔つきがなんとも言えず可愛らしいのです。
このモデルの名前の由来は、映画『Jay and Silent Bob Strike Back』に登場するサルの名前が「Suzanne」だったことから来ています。開発当時、この名前を使うことに決めたのは、Blenderの開発チームが「堅苦しくない、ユーモラスな文化」を大切にしていたからです。
なぜ猿?その背景にある遊び心
スザンヌがなぜ猿なのか、という疑問を抱く人も多いと思います。実はこれには深い理由というよりも、Blenderらしい“遊び心”が詰まっています。
商用の3DCGソフトウェアが精密なテクニカルモデルを多く備えているのに対し、Blenderはオープンソースで自由度が高く、クリエイター主導で発展してきた経緯があります。その中で「テスト用のモデルに、ちょっとふざけたキャラクターを使うのもアリじゃない?」というノリが生まれたのです。
さらに、猿というモチーフは人間に近く、目・耳・口といったパーツがしっかりあるため、マテリアルのテストやライティングの検証にちょうどよい形状になっています。
スザンヌ・アワードって知ってた?
Blenderの年次カンファレンス「Blender Conference」では、「Suzanne Awards」という賞が存在します。この賞は、Blenderを用いた優れたアニメーションや短編映像に贈られるもので、まさにスザンヌの名を冠する名誉ある賞です。
このことからもわかるように、スザンヌは単なるお遊びキャラではなく、Blenderの精神や文化の象徴とも言える存在なのです。
スザンヌの使い道いろいろ
実際にスザンヌをどう使うのか?その用途は意外と幅広く、初心者から上級者までに愛されています。
- ライティングのテスト:ライトの位置や強さ、シャドウの出方を確認するのに最適。
- マテリアル・シェーダーの実験:肌、金属、ガラスなどのマテリアルを試すときに便利。
- モディファイアやパーティクルの挙動確認:サブディビジョンやスムーズ、物理演算などの効果を即座にチェックできる。
- ノード設定のデバッグ用:複雑なノードネットワークを組む際の出力確認に。
- トポロジーの練習:スカルプトやリトポロジーの練習素材としても適しています。
また、コンポジティングやVFXの練習として、背景と合成したり、モーションブラーを確認したりするのにも役立ちます。
スザンヌの進化とコミュニティでの活用
Blenderのバージョンアップに伴い、スザンヌもマイナーながら改良が加えられています。例えば、メッシュのクオリティやポリゴンの分布などが微調整され、より実用的な形になってきています。
さらに、Blenderのユーザーコミュニティではスザンヌを使ったコンテストやミームがしばしば登場します。SNSでは「#SuzanneChallenge」というタグで、さまざまなアーティストが創造的にスザンヌを変身させた作品をシェアしています。これを見るだけでも、Blenderの文化の奥深さを感じられます。
スザンヌを通じてBlenderの魅力を感じよう
Blenderの魅力のひとつは、その自由さと遊び心。そしてスザンヌはまさにそれを象徴する存在です。見た目はちょっとユルいけど、実はとても重要な役割を担っている…そんなキャラ、なんだか愛着が湧いてきませんか?
これからBlenderを始める人も、すでに使っている人も、ちょっとした合間にスザンヌで遊んでみてはいかがでしょう?きっと、Blenderの世界がもっと楽しく、身近に感じられるようになるはずです。


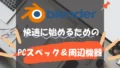

コメント